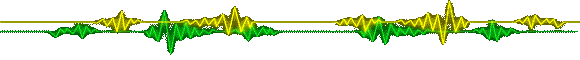
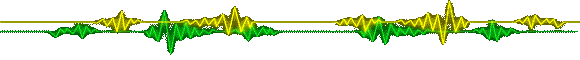
[トップページ] [プロフィール] [業績と研究] [趣味と特技]
ご注意=かなり長くなっていますので、時間に余裕のある方はお読み下さい。

1942年6月4日に零細農家の次男として京都府相楽郡西和束村大字白栖小字下出49の1において生まれる。終戦が3歳の時であったから、戦争に関する記憶はほとんどない。おやつが欲しい年齢であるが、購入できる品物も少なく、その上小遣いももらえなかった。ただ、運良く父がアメリカ軍の支給品であるチョコレートを配給で引き当てたときのみ、兄弟で分け、ほんの少し食べることができた。しかし、農家であるため、苺、グミ、西瓜、葡萄、蜜柑、柿、栗といった果物をもぎ取って食べることができたので、今もその味が忘れられない。
物心が付いたときから、我が家では米半分、麦半分の麦飯であったが、これが嫌でたまらなかった。そのことを思い出して、大学院時代に話すと、現在神戸学院大学で哲学を教えている友人が本気で怒って「何を言っているんだ。僕らは麦飯なんか口にできなかった。豆粕ばかり食べていたんだ」と言って私を諭してくれた。当時はひどい麦飯でも恵まれていたのだ。
父の実家が瓦製造業を営んでいるので、その仕事もしていた父が農地解放を契機として開墾を始め、宇治茶の生産に切り替える決心をした。これは少なくとも数年間は父の現金収入がほとんどないことを意味したので、我が家は赤貧洗うが如しの生活に陥った。長姉が農業協同組合に勤めていたので、父はその収入に頼ったのである。
小学校時代

雑草のように育った私は手のつけられない腕白そのものだったようである。武勇伝は数限りなくあるので、小学校の同窓会には出席しにくい。次姉の夫はしばしば「お前達の学級は西和束小学校始まって以来の悪童の集まりだった」と言っていたので、先生は大変であっただろうと思っている。そんな悪童も卒業する頃には、先生、両親、社会によってかなり矯正されていた。
特に、2年生の始業式の直後、私は数人の友達と一緒に工事用のトロッコに乗って、大怪我をした。雨が降っていたので、工事をしていなかったのである。坂にさしかかったとき、雨でトロッコは速度を増したので、ブレーキのかけ方を知らない友達は怖くなって皆飛び降りたが、私はそのまま乗っていて、急カーブで下の川へ振り落とされたのである。そして、河床に散在していた護岸工事に使う三角形をした大きな石の角で頬を大きく切り裂いたのである。頬が変だと思って手をやると、その手が口の中まで達していた。頭が割れなかったことが不思議なくらいであったようである。父から何度も「乗るな」と注意されていたにもかかわらず、乗ったのであるが、いつもすぐ殴る父が何も言わずに背負って病院へ連れていってくれた。悪いことをしたとき、叱られないことほどばつの悪いことはない。少しは父の言うことを聞くきっかけになった。その後、現在はかなり後退しているけれども、頬に残っている傷跡は時々心の傷となって人生の軌道修正を促してくれた。
また同じく2年生のときである。先生が「次の時間は歌のテストをしますので、音楽室へ入りなさい」と言われたのを聞いて、音痴の私は歌うのが嫌なので、校庭の上の崖に生えている大きな松の木に登っていた。先生はそのことを知って駆けつけ、顔を青ざめながら「正容さん、下りてきなさい」を1時間中繰り返しておられた。音楽室では悪童どもが勉強しないで大騒ぎをしていたようである。この時もあまり叱られなかった。女の先生は動転されて,怒る気力がなくなっていたのかも知れないが、叱られて当然のとき、叱られないことは薄気味悪く、悪かったと思うきっかけになっていた。
校長先生は1週間に2度も3度も職員室で立たされる私を見て、「またか」と言われるだけであった。そして、執務中の机から時々眼鏡越しに上目遣いで見つめられると、私は身の縮む思いがした。校長先生はこの無言の叱責が私に大きな効果を持っていることを知っておられたのである。お陰で、現在も眼鏡をかけた人が怖く、眼鏡越しに上目遣いをされると、恐怖感が蘇るのである。
6年生になって新聞少年になった。前の年、昭和28年8月15日未明に発生した南山城水害で約250名が亡くなり、地獄の恐怖を味わった。山津波が襲ったのである。このため我が家の水田が全て流失したので、再び貧困生活が待ち受けていた。朝5時に起き、仮設道路を3キロ歩いて新聞を受け取り、配達を終えると7時過ぎであった。中学2年生まで続けたが、これで忍耐心と持久力を養うことができた。現在はほとんど雪は降らないが、当時は毎年2、3回は大雪が降り、翌日の配達ですら難渋した記憶がある。
